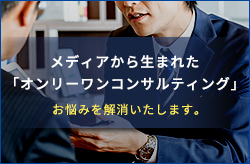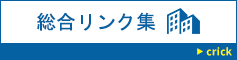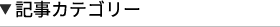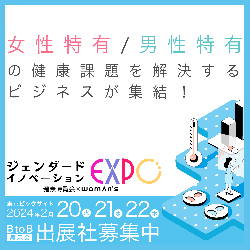前回はアーユルヴェーダから見る病気の成り立ちを、新型コロナウイルスを参考にお伝えいたしました。
いかに発症する前に予防対策が必要かをご理解いただけたのではないでしょうか。
5000 年もの歴史があるアーユルヴェーダは、予防医学としても昨今再認識されています。
さて、7 月から8 月にかけて、アーユルヴェーダ的には消化力が落ちやすい時期だと考えています。食欲が減り、体力が落ちてくると免疫力も下がってきます。
7 月はまだ梅雨もあり、湿気と暑さで体力を奪っていきます。
また、食品も傷みやすく、食材選びや調理にも慎重になるでしょう。
健康を考えるとき、アーユルヴェーダでは、消化力をとても大切に考えます。
消化の力をアーユルヴェーダでは「アグニ」と言って五元素のうちの「火」の力となります。
「火」は変化を生むエネルギーでもあり、食べた食物を栄養素へと変化させるために、「火」の力を使う「アグニ」で消化していきます。
ですが、季節的にも暑さが増し、「火」のエネルギーが生活の中で増えていきます。
そのため、身体の中の「火」も反応して、過剰になり、「アグニ」が乱れてくるという現象が起きてきます。
梅雨時期からお腹を壊しやすくなる人が増えるのもそういった背景があります。
この時期は「火」のエネルギーが過剰になりやすい、「ピッタ」は要注意です。
この消化の「アグニ」=「火」の力が弱いと、消化力が弱くなったり、食べたものが十分な栄養へと転換されません。
逆に、消化の炎が強いと消化力、代謝力もあがり、食べたものが必要な血液や筋肉などの組織に変化し、オージャスという私たちの活力を生んでくれます。
アグニの力は私たちにとって、とても重要です。
よく、テレビ番組でも高齢者の方に健康の秘訣を聴くと、よく食べることと伝えています。
よく食べるから健康なのもありますが、逆にアグニの力が強いからこそ、健康で食欲も旺盛なのかもしれません。
瀬戸内寂聴さんが、90 歳を超えても、お肉が大好きで食欲も旺盛なのはアグニの力が強いからかもしれませんね。
この暑い時期は自身の「アグニ」をよく観察し、消化の良いものを選んで夏を乗り越えましょう。
これからも、アーユルヴェーダライフを楽しんでいきましょう。